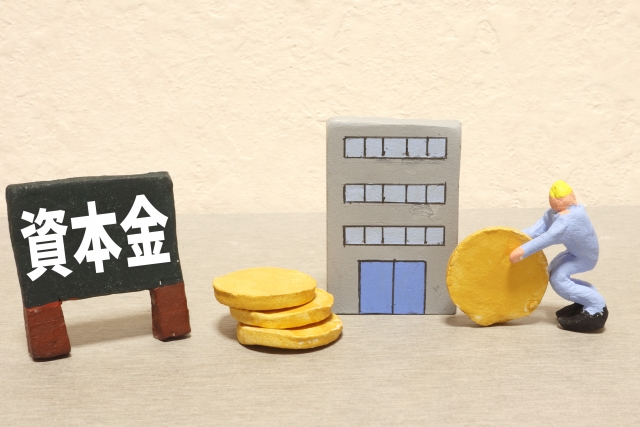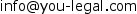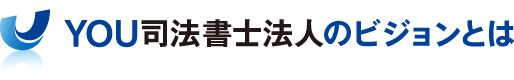こんにちは、YOU司法書士事務所です。
株式会社などで資本金を増やすことを増資といいますが、逆に資本金を減らすことを減資といいます。増資の方が耳にする機会は多いと思いますが、新聞やニュースで大手企業が減資を行ったということを耳にすることもあるでしょう。
一般的に増資の方が良いイメージがあり、減資をすることはあまりよくないことのように思われがちですが、実は減資をすることで、さまざまなメリットを得ることができるのです。
今回のコラムでは、減資とはどのようなものか、その定義やメリットとデメリットについて、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説します。また、実際に減資を実施する場合の手順・おおまかなスケジュールも解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
資本金の減資とは?
減資とは、会社の資本金を減らす手続きのことを指します。ここでいう「資本金」とは、会社を設立する際に株主から集めたお金で、事業経営の基盤となるものです。
「減資を行うと、株主の持ち分が減少する?」と思われがちですが、減資は帳簿上の数字を調整するだけのときもあり、発行済株式の数が実際に減少するとは限りません。
減資の種類には「有償減資」「無償減資」の2つがあり、減資を行う主な意味・目的は以下の3つです。
- 株主への払い戻し
資本金の一部を株主へ払い戻すこと
- 欠損金への補填
累積赤字を解消による経営の立て直し
- 節税
法人税などの節税につながる
減資の種類とメリット・デメリット
減資には以下の2種類があります。
- 有償減資
実際に資金を減らす方法
- 無償減資
帳簿上の数字を動かすだけで、実際の資金は減らない方法
それぞれの意味やメリット・デメリットを解説します。
有償減資
有償減資とは、実際に資金の減少がともなう減資です。
この手法は、主に「株主への払い戻し」目的で実施されます。資本金の減少によって生じた余剰金を、株主に配当金などの形で払い戻し、その結果会社の現預金も減少する仕組みです。
具体例でみていきましょう。減資前の会社の財務状況が以下のとおりだったとします。
【有償減資前】
現預金:10億円
負債:4億円
資本金:6億円
この会社が株主への還元として1億円を減資した場合、資本金が1億円減ります。そして同時に、現預金も1億円減少。その結果、減資後の財務状況は次のようになります。
【有償減資後】
現預金:9億円
負債:4億円
資本金:5億円
有償減資のメリット
有償減資の1番のメリットは、株主に対して配当金を出すことができる点です。
通常、会社が利益を上げられなかった場合、株主への配当は「無配当」として見送られることがあります。しかし株主との関係を維持し、信頼を損なわないためには、利益が出ていない状況でも配当を支払いたいと考えることがあるでしょう。
ここで活用されるのが有償減資です。法律上、資本金そのものを直接配当金として支払うことはできませんが、有償減資を行うことで生じた剰余金を原資とすることで、株主に配当を支払うことが可能になります。
有償減資のデメリット
有償減資のデメリットは当たり前ですが、会社の財産が減ってしまうことです。
会社の財産が減ってしまうことで、将来的な投資が難しくなることはもちろんですが、金融機関からの融資の審査が厳しくなるといったデメリットがあります。将来の会社の成長性を考えても今後の資金繰りが苦しくなるといったリスクもあります。
無償減資
無償減資とは、有償とは逆で資金の減少がない減資のことです。無償減資は、主に「欠損金への補填」「節税」を目的としています。
資本金を減らして決算上の赤字(欠損金)に充てることで、財政状況を健全化し、経営を立て直すきっかけを作ることができます。
具体例で説明します。減資前の会社の財務状況は以下のとおりです。
【無償減資前】
現預金:10億円
負債:4億円
資本金:7億円
欠損金:1億円
ここで、欠損金1億円を補填するために無償減資をしたとします。この場合、資本金を1億円減少させ、その分を欠損金の補填に充てます。無償減資は資金が減少しない手続きであるため、現預金には影響がありません。結果として、減資後の財務状況は以下のようになります。
【無償減資後】
現預金:10億円
負債:4億円
資本金:6億円
欠損金:0円
無償減資のメリット
無償減資の主なメリットは、以下の2つです。
- 経営の立て直しにつながる
- 節税効果がある
会社の赤字経営が続くと、決算上の「欠損金」がたまります。この欠損金が多いままだと、金融機関の融資の審査が不利になり、お金を借りられなくなるかもしれません。
黒字を出さないと欠損金は消えないのですが、無償減資で欠損金を穴埋めすることも可能です。資本金を取り崩してこの欠損金を補填することで、欠損金が相殺されます。その結果、会社の財務状況が改善されるため、金融機関の審査が通りやすくなるでしょう。たとえば、新たな投資や事業拡大を検討する際にもプラスに働きます。
また、無償減資は節税効果が期待できることもメリットです。
資本金が1億円を超える大企業と1億円以下の中小企業では、税制上の優遇措置に差があります。無償減資によって資本金を1億円以下にすることで、中小企業向けの優遇措置を利用でき、税負担を軽減できるのです。
無償減資のデメリット
無償減資のデメリットは、企業の信用が低下するリスクがあることです。
企業の信用は売上や利益をはじめ、さまざまな要因で判断されますが、特に中小企業においては資本金が多いほど信用力が高いとされます。無償減資によって資本金が減少することで、取引先や株主から「経営が厳しいのでは?」と思われてしまうかもしれません。
外部から見た企業の安定性や信頼性が低く評価され、新規取引先との契約や融資の実行が難しくなることも考えられます。
資本金の増資とは?
増資とは、資本金の額を増やす手続きのことです。減資と同様に以下の2種類がありますが、一般的に「増資=有償増資」を指すことが多いようです。
- 有償増資
企業が新たに株式を発行し、株主から出資してもらうこと。 - 無償増資
企業の資産(準備金や剰余金)を資本金に振り替えて株式を発行すること。
増資の主な目的は「資金調達」「企業の信用力の向上」です。
増資することで、企業は事業拡大や新たなプロジェクトに必要な資金を調達できます。また、増資により資本金が増えると外部からの信用を得やすくなり、新規取引先との契約や金融機関からの融資がスムーズになります。
減資との違いについて?
増資と減資は仕組みが真逆です。増資は資本金を増やす手続きなのに対して、減資は資本金を減少させる手続きです。
また、すでに解説していますが、増資と減資は以下のように目的も異なります。増資は「資金調達」「信用力の向上」などが目的です。その一方で減資は「株主への払い戻し」「欠損金への補填」「節税」などが挙げられます。
増減資とは?
増減資は、増資と減資を同時に行うことです。
一例として、新たな株式の発行によって資金調達を行った後、増加した資本金と同額の減資を行い、資本金を元の水準に戻すケースが挙げられます。資金調達の必要性はあるものの、増資に伴うデメリットを回避したいときに有効です。
減資の会計処理について
「有償減資」と「無償減資」では、それぞれ会計処理が異なります。有償減資は株主へ資金を払い戻す処理を行う一方で、無償減資は帳簿上の数字を整理するだけです。具体的な仕訳例をみていきましょう。
有償減資の場合
有償減資は、資本金を減らして株主へ払い戻す手続きです。しかし会計法のルールにより、「資本金を直接減額して株主に支払う」ことはできません。以下のとおり2段階の処理を行います。
①「資本金」を減らして「その他資本剰余金」へ振り替える
②「その他資本剰余金」を減らして株主へ払い戻す
例えば100万円の有償減資を行い、株主に払い戻すケースでは、以下のように仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
資本金 | 100万円 | その他資本剰余金 | 100万円 |
その他剰余金 | 100万円 | 未払配当金 | 100万円 |
なお、株主に配当金が支払われる際は、未払配当金を減らす仕訳も行います。普通預金口座から配当金を支払った場合の仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
未払配当金 | 100万円 | 普通預金 | 100万円 |
株主に資金を払い戻す際、支払額の一部が「みなし配当」として、税金の対象になることがあります。みなし配当とは、株主に支払うお金のうち「株式の価値を超えて支払われた部分」のことであり、税法上の配当とみなされます。
無償減資の場合
無償減資は、資本金は減少するものの株主への返金は行わない手続きです。会社から現金などの資産が出ていくわけではないため、帳簿上の数字の移動にすぎません。
欠損金への補填があるケースとないケース、それぞれの仕訳例をみていきましょう。
欠損金への補填がない場合、会社の資本金を減らして、その分を「その他資本剰余金」へ振り替えるだけです。この場合、会社の財務状況に変化はありません。
例: 株主総会にて、資本金100万円の無償減資が決議された場合
借方 | 貸方 | ||
資本金 | 100万円 | その他資本剰余金 | 100万円 |
会社の過去の損失(欠損金)を補うために無償減資を実施するケースは、以下のように2段階の会計処理を行います。
①「資本金」を減らして「その他資本剰余金」へ振り替える
②「その他資本剰余金」を使って繰越利益剰余金(マイナス分)を補填する
例:株主総会にて、資本金100万円で欠損金の補填が決議された場合
借方 | 貸方 | ||
資本金 | 100万円 | その他資本剰余金 | 100万円 |
その他資本剰余金 | 100万円 | 繰越利益剰余金 | 100万円 |
減資に必要な手続きと流れ
減資を行う際には、株主総会の決議や債権者保護手続きなどが必要です。手続きの流れをチェックしましょう。
株主総会の特別決議
減資は株主への影響が大きいために、原則として株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議は、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、その3分の2以上が賛成しなければなりません。この総会で決定すべき事項は次のとおりです。
- 減少する資本金の額
- 減少資本金を準備金とする場合のその旨および準備金とする額
- 減資の効力が生じる日
債権者保護手続き
減資をするときには、原則として債権者保護の手続きが必要です。具体的には、官報での公告と債権者への個別催告を行います。なお、電子公告や日刊紙への掲載を公告方法として定めている場合は、これらの方法で公告することで個別催告を省略可能です。また、債権者が異議を述べられる期間を1か月以上設けることが法律で定められているため、減資の手続きには最低1か月以上の期間が必要となります。
減資の効力の発生時期
資本金減少の効力が発生する時期は、原則として株主総会の特別決議で定められた効力発生日とされています。ただし、その日までに債権者保護の手続きが完了していない場合は、手続きが終了した時点で減資の効力が生じる仕組みです。
登記申請
資本金減少の効力発生日から2週間以内に、管轄する法務局へ変更登記の申請を行います。目的変更の手続きには、登録免許税の3万円が必要です。また2週間以内に登記を行わないと、100万円以下の過料が発生する可能性がありますので注意しましょう。
登記申請に必要な書類
「株式会社変更登記申請書」に、株主総会議事録や株主リストを添付のうえ申請する必要があります。申請書は法務局のHPからダウンロード可能です。
一般的に必要な添付書類は、下記のとおりです。株主総会議事録
- 株主リスト(株主の氏名・名称・住所・議決権数などを証する書面)
- 一定の欠損の額が存在することを証する書面(定時株主総会の普通決議の場合)
- 公告及び催告をしたことを証する書面
- 委任状(代理人に申請を委任した場合)
もし異議を述べた債権者がいた場合は、以下の書類も必要です。
- 弁済・担保・信託したことを証する書面
- 減資しても異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面
なお、異議を述べた債権者がいない場合、申請書に「異議を述べた債権者はない」と記載します。
まとめ
今回の記事では有償減資・無償減資のメリットとデメリット、そして手続きの流れについて解説をいたしました。
減資と聞くとネガティブに捉える方もいらっしゃいますが、ポジティブな要素もたくさんあることがご理解いただけたと思います。長く会社経営を続けていく中では、減資という選択肢もあるかもしれませんので、ぜひ今回のコラムで解説した減資のメリットやデメリットをよく理解した上でご自身の会社の状況に合った選択をしていただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラムの「減資とは?有償減資/無償減資のメリット・デメリットや資本金を減らす理由を解説」のテーマの解説は以上になります。
YOU司法書士事務所では、今回のコラムで解説した減資に関する手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。
お電話・メール・LINEにて承っております。
業務のご依頼をいただくまでは費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。